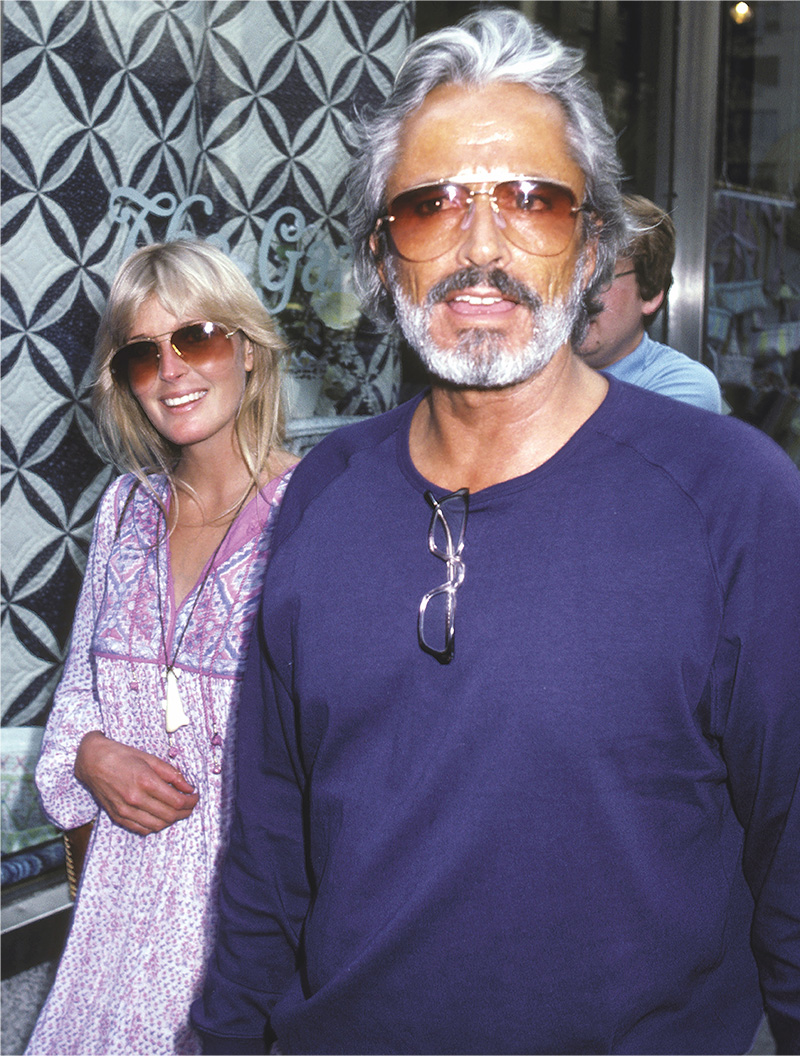January 2017
COUP DE GRACE
グレースという贈り物

大公夫妻の結婚式で、祭壇にて(1956年4月)
ついに出会うグレースと大公 リヴィエラで『泥棒成金』の撮影に臨んだグレースは、再びこの地を訪れていた。一方、1949年に総協議会のメンバーとしてローマに呼ばれたタッカーは、その後、若き大公の専属司祭を務めるためにモナコへ派遣されたのだが、それより以前に、グレースの故郷であるフィラデルフィアで過ごしたことがあった。タッカー神父が、まだ天の配剤を信じていたとすれば、まばゆいばかりのグレース・ケリーをモナコに連れてきたのは、神の御手に他ならなかっただろう。
神父はレーニエ大公にこう説いたらしい。「戦争中にヨーロッパの王が次々と王座を失った以上、従来より範囲を広げて花嫁探しをする必要があります。アメリカ中心の世紀の真っただ中にある今、アメリカ人女優と結婚することは大公にとって決して悪くない選択です。そしてできれば、公妃役をもっともらしく演じられる名女優がいいでしょう」と。
ふたりの顔合わせは、十分に和やかだった。グレースと大公が文通を始めると、互いの距離はたちまち縮んだ。大公がボルティモアを訪れたのも、健康診断というのは名目だけで、実はケリー嬢を口説くためだったのだ。しかし、ふたりが打ち解けてゆく一方で、大公は乗り越えるべき文化の違いがあることを感じていた。「おそらく、こんな風に説明すべきだろうね」と、レーニエ大公は語った。
「多くのモナコ人がアメリカ人と聞いて思い浮かべるのは、キャデラックでオテル・ド・パリに乗り付けるような、少々風変わりな人種だけだった。同様に、イギリス人と聞いてイメージするのは多分、婦人のスリッパからシャンパンを飲んでいる貴族の姿だろう。こうした人たちが、普通よりも少し個性的な例外だということをなかなか理解してもらえなかった。その結果、必然的に不信感が生まれたし、公妃が映画スターであるという事実もまた、年配の国民の多くを驚かせた」