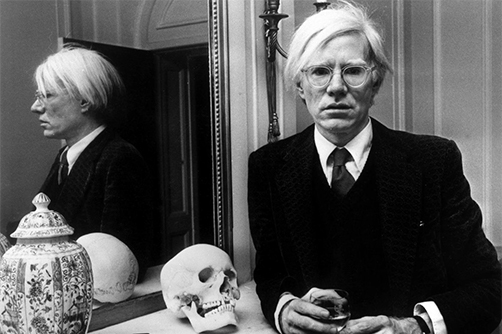RETURN OF THE PRODIGAL
フジタ、その愛と芸術
August 2018
「狂乱の時代」と形容される1920年代のパリで寵児となり、放蕩三昧の後に従軍生活を送り、
亡命するように日本を去ったその生き様と作品が、ようやく曇りない視点から再評価されるに至ったのだ。

Léonard Foujita / 藤田嗣治画業だけでなく、渡欧間もない若き日の藤田嗣治はロンドンに滞在中、セルフリッジズでスタイリストとして生地デザインも手がけた。彼は生涯、身に着けるものはすべて自らの手で仕上げていたという。彼がデザインした生地で誂えた衣装を纏って、あのマリア・カラスがミラノのスカラ座の舞台に立ったこともある。
透き通るような乳白色に格別の艶めかしさ エコール・ド・パリの画家の中でも、アメデオ・モディリアーニや若い頃のパブロ・ピカソと並んで、同時代に最も華々しい成功を収めたひとりとして、後のレオナール・フジタこと藤田嗣治は記憶されている。西洋の画壇の中心であった当時のパリに、独自の作風を認めさせた藤田は、今風にいえば「ワールドクラスの大活躍」をした訳だが、画業だけで彼を評価することを難しくしていたのが、女性関係を含む前半生のスキャンダラスな行状と、第二次大戦中に旧帝国陸軍の従軍画家として数々の戦争画をも遺した事実が、後半生につきまとったことだ。
戦後の日本で、旧陸軍の協力者にして戦前戦中のイデオロギーの体現者であるかのように糾弾されたことは、彼の生涯に暗い影を落とし、追われるかのように日本を離れる要因のひとつとなった。
藤田は元より親戚縁者にも軍人が多く、軍医の父をもつ家柄に生まれた。長じて陸軍軍医総監にまで上りつめた父の前任者は森鷗外で、官立東京美術学校(現東京藝術大学美術学部)へ進学を薦めたのも森鷗外だったという。そこで出会った恩師は、薩摩出身でパリにて絵を学んでいた黒田清輝だった。
いわば「明治のエリート」の出である藤田が、日本に戻れば早々にしがらみにからめとられることは、不可抗力とはいわないまでも自明の理といえた。黒や影を多用する学生時代の藤田の画風は、印象派に強く影響された黒田からまったく評価されなかった。きわめて明治色の強い、権威主義や規律といったものが、渡仏前も帰国後も藤田を縛り、抑圧したのとは対照的に、フランスの自由な空気は生涯を通じて彼を感化し、若き日に芸術家としての自己を確立させただけでなく、宗教画や宗教的テーマを通じた晩年の自己完成をも促したといえる。

マネの『オランピア』よりズームした構図で、ユキの上半身を捉えつつ、藤田独特の乳白色のニュアンスをよく示す作品。
Femme allongée, Youki Léonard Tsu guharu Foujita, 1923, huile sur toile Collection particulière
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2018