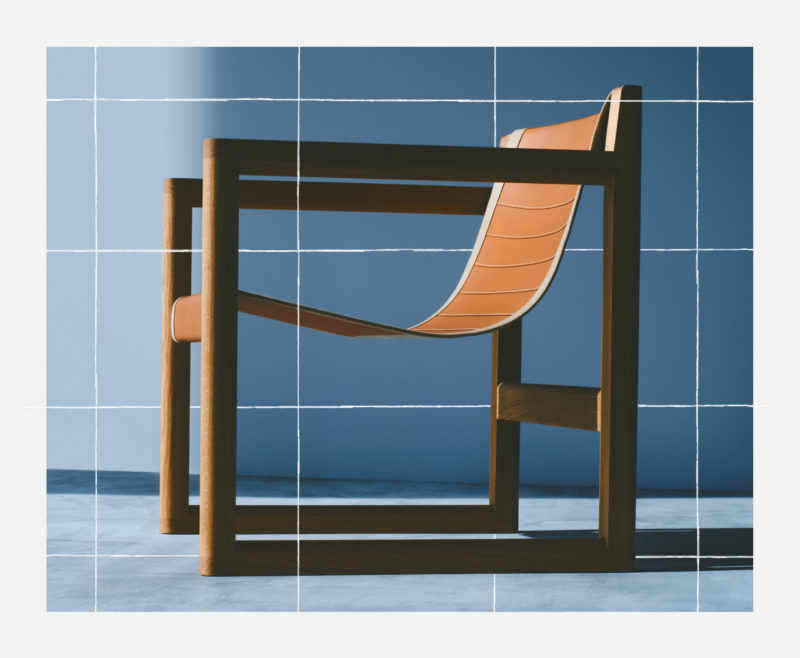エルメス本社の副社長まで務めた日本人
齋藤峰明さん
Tuesday, March 10th, 2020
齋藤峰明さん
シーナリー・インターナショナル代表
text kentaro matsuo photogaphy tatsuya ozawa

欧米のラグジュアリー・ブランドに関わった日本人で、最も成功したビジネスマンの一人、齋藤峰明さんのご登場です。なにせあのエルメスの“フランス本社の”副社長まで務めた方ですから。
エルメスといえば、私は“テーマ発表会”を思い出します。エルメスは毎年テーマを決めて、そのテーマに沿ったアイテムを発売したり、イベントをしたりするのが恒例なのですが、齋藤さんがエルメスジャパンの社長をなさっていた頃、1990〜2000年代のエルメスは、顧客やジャーナリストを呼んで、日本でも華やかなテーマ発表会を催していたのです。
例えば、“河”がテーマだったシーズンは、何十人ものプレスを連れて上海へ行き、揚子江で花火を打ち上げました。“ダンス”がテーマだった年は、大阪で一夜限りの巨大クラブを出現させ、もんたよしのりに『ダンシング・オールナイト』を歌わせました。
なかでも印象的だったのが、“ホームパーティ”がテーマだったときの発表会です。エルメス銀座本店を舞台にして、実際のお店やブランドのスタッフが、手作り料理をサーブし、楽器を奏で、ハイライトは全員で大合唱をするという内容でした。
「モーツァルトの難曲“アヴェ・ヴェルム・コルプス”をラテン語で、“アヴィニオンの橋の上で”をフランス語で歌おうということになりました。作曲家・三枝成彰さんにコーラスの指導をお願いし、半年もの間、店が終わった夜9時から、皆で練習をしました。もちろん私も一緒に歌いました。数ヶ月経つと、だんだん声も出てきて、ハーモニーが生まれるようになった。“これはいいぞ!”と思って、三枝さんに聞いてもらったら『こんなんじゃ、ぜんぜんダメだ! 出来ないなら、止めたほうがいい!』とまで言われてしまった。なんでこんな厳しい人に指導をお願いしたのか、すごく後悔しましたね・・。そこで皆に『もう、やめようか?』と相談しました。ところがスタッフは全員『やります!』と言ってくれた。そこで夜に加えて、開店前の朝にも練習することにしたのです。皆なにかに取り憑かれたようでしたね。そしてイベントの直前に、もう一度、三枝さんに聞いてもらったら、一転して『よし、いいぞ! 当日は溌剌と歌おう!』とすごくホメられた。彼はあえて厳しい態度を取っていたのです」
その結果は、素晴らしいものでした。サーブしているスタッフが突然歌い出し、それが大コーラスへと発展していくのです。本物の合唱隊顔負けの声量とハーモニーに、ただただ驚いたのを覚えています。
「いつも接客をしているスタッフが、一生懸命歌うのを見て感激し、涙を流してくれるお客様もいました。すべて終わった後、“もう一度歌おう”ということになり、今度は自分たちだけで、ポロポロと泣きながら合唱しました。あの時こそ、“やれば、やっただけのことができる”と感じたことはなかったですね。その年の“ベスト・パーティ・オブ・ザ・イヤー”にも選ばれたんです」

私的には、ベスト・パーティ・イン・マイ・ライフですね。イベント業者に丸投げのパーテイが多い中、あんなに手作り感溢れる(しかもレベルが高い)おもてなしは、後にも先にも経験したことがありません。
それは、人に慕われる齋藤さんのお人柄の賜物でしょう。そして当時のエルメス会長だった、故ジャン・ルイ・デュマ・エルメスさんの影響かも知れません。
「毎年のテーマは、ジャン・ルイが考えていました。16年間一緒に仕事をしましたが、あんなにすごい人は見たことがありません。ビジネスとアート、両方に精通しているのです。彼の言葉に『頭は雲の上に、足は地上に』というのがありますが、それを地で行く人でした」
私もデュマ氏には、数回お目にかかったことがあります。いつもカバンの中に水彩絵具のパレットを携帯していて、なにか思いつくとサラサラと絵を描くという、まるでアーティストのような人でした。
銀座にそびえるフラッグシップショップ“メゾン・エルメス”は、齋藤さんとデュマ氏が、力を合わせて作り上げたものです。
「日本通だったジャン・ルイは、どうしても銀座に店を作りたがっていました。1997年に土地を取得したのですが、当時は今のような巨大ブランドではなかったエルメスにとって、それは莫大な投資でした。本国のファミリーに、“なぜ銀座なのか?”を説明したのは、私なのです。『ギンザはトーキョーのフォーブル・サントノーレなのだ』とか言って(笑)」
ガラスブロックを使った外観で知られる建物をデザインしたのは、有名建築家、レンゾ・ピアノさんですが、彼に頼むことは、ジャン・ルイさんの奥様、レナ・デュマさんが思いついたそうです。
「私とデュマ夫妻の3人で、定宿だったホテル西洋のスィートでミーティングをしていたとき、インテリア・デザイナーをなさっていた奥様が、突然『設計は、レンゾ・ピアノがいいんじゃないかしら?』と言ったのです。その時は、誰も面識がなかったのですが、ジャン・ルイは、いきなり国際電話をかけて、レンゾさんと連絡を取ろうとしていましたね・・」
しかし、ここからが苦労の始まりでした。
「ジャン・ルイとレンゾは、同じ年だったこともあって、すぐに意気投合していました。しかし、そこからが大変だった。ふたりともビルではなく“作品”を作る気でいたのです。まずビルの名前からして、“エルメス・ビル”ではダメだという。エルメスは、メゾンなのだから“メゾン・エルメス”にしろという。私としては、なんだかマンションの名前みたいで嫌だったんですけれど・・(笑)。いまでこそ、“メゾン云々”という名前は普通になりましたが、当時はそんな名前を付けているブランドは、どこにもなかったのです」
「建物では、さらに苦労しました。レンゾ・ピアノという人は、とにかくすべてを自分でデザインして作るのです。例えボルト1本でも。ところが日本の建築基準法は、基本的に実績のある既製品しか使ってはいけない。そこで部材について、いちいち許可を取らなければいけないので、普通の建物を建てるより、倍の時間がかかりました。あのガラスブロックは、フィレンツェ郊外にある工場で作られたものなのですが、現地に何度足を運んだかわかりません。最終検査の際、工事を担当している会社の人に『これが通らなかったら、もう出来ません・・』とまで言われました(笑)」
銀座のランドマーク、メゾン・エルメスは、ジャン・ルイ、レンゾ、そして齋藤さんの「子供みたいなもの」だそうです。

スーツは、エルメス。
「実はこれは、試作品なのです。エルメスにいた頃は、よくメンズのデザイナー、ヴェロニク・ニシャニアンに頼まれて、新作を試していました。一応モデルサイズなので・・」
180cmをゆうに超える、長身の痩身にお似合いです。
タイも、エルメス。
「エルメスのタイは、もう何百本と持っています。23年間もいましたから、毎年数本ずつ手に入れても、そのくらいの数になります。発色がよく締めやすくて、いまだに捨てられないのです」
シャツは、パリの小さなシャツ店でオーダーしているもの。
「エルメスにいた頃は、すべてエルメスしか着られなかったので、他の店のものも着られるようになって、ちょっと嬉しいですね(笑)」

鞄は有名なエルメスの名作“サック・ア・デペッシュ”。私の憧れです。
「これは二代目のサック・ア・デペッシュです。一代目は16年間毎日使いました。これは12年間くらい経っています。もう体の一部、相棒のようなものです」
特製のノートカバーと名刺入れもエルメス。
「ノートカバーは、エルメスの職人に言って、特別に作ってもらったのです。中身は伊東屋で売っている100円のノートですよ(笑)」

シューズは、ジョンロブ。言わずと知れたエルメス傘下の名靴です。
「エルメスには、今ではイタリア製のオリジナルもありますが、私のような古くからのファンは、ジョンロブが好きだという人が多い。カッチリしていて、何より長持ちするのです」

さてフランス本国の副社長まで務められたのは、その抜きん出た語学力とインターナショナル性ゆえ。しかし都立青山高校に在学中、最初にフランスへ行こうと思い立ったのは、決して深く考えた結果ではありませんでした。
「私が高校生だった頃、1960年代の後半は、映画はヌーヴェルバーグ、書物はサルトルやボーヴォワール、演劇はテアトル・デュ・ソレイユなど、カッコいいもの、新しいものはなんでもフランスからやってきていました。そのうち高校がバリケードで封鎖されてしまい、授業がなくなった。仕方がないので、渋谷のジャズ喫茶へ通って、友達と話し込んでいました。ある夜、ゴダールの話で盛り上がって『よし、皆でフランスへ行こう!』ということになったんです。それがきっかけですかね。実際に行ったのは、私だけでしたけど(笑)」
入学なさったのは、名門ソルボンヌ大学です。
「大学へ入る前は、半年間毎日10時間勉強しました。あんなに勉強したのは、あれが最初で最後ですね(笑)」
ところがせっかく入学した大学でも、すぐにストが始まったそうです。
「そこで三越のパリ店でアルバイトを始めたのです。当時は百貨店の黄金期で、日本からお得意様を連れてきては、ノートルダムでコンサートをやったり、ヴェルサイユ宮殿で花火を打ち上げたりしていた。たまたま一番フランス語が出来るのが私だったので、そういった交渉事の一切を任されました。バイトなのに、ノートルダムの大司祭と交渉したりしていましたよ(笑)」
その後、一旦は商社に就職するも、三越の社長から呼び戻されて、三越のフランス駐在員となります。
「ファッションはもちろん、食品、家具、クルマまで、フランスのいいものを探して日本に紹介していました。とても面白い仕事で、22年間続けました。逆に、日本のいいものをフランスに紹介するSHIZUKAというショップを手掛けたりもしましたね」
そして、前出のジャン・ルイ・デュマ・エルメスさんと運命的な出会いをします。
「エルメスから転職の誘いがあったのです。でもよく話を聞いてみると、職場は日本だった。私はそれまでフランスでしか働いたことがなかったから、日本の社会なんて無理だと思いました。そこで一旦はお断りしたのですが、もう一回電話があって、やっぱりどうしても来てほしいという。そこでデュマさんとお会いしてみたのです。彼はいきなり私をエルメスのアトリエへ連れて行きました。そして職人たちと話を始めた。そうしたら、デュマさんと話をする職人たちの横顔が実に生き生きとしていて、思わず魅せられてしまった。するとデュマさんは私の方を向いて、『来週、幹部を集めた会議をやるからお前も来い』という。その会議へ行ったら、皆に『お前を歓迎する!』といわれた。まだ、返事をしていないにも関わらず、です(笑)」
しかし結局、デュマさんの魅力には抗えず、エルメスへ移籍。前出のエピソードへと繋がるわけです。
現在では、ご自分の会社シーナリー・インターナショナルを立ち上げられ、日本と世界の橋渡し役をされています。
「シーナリーとは、風景や景観のことです。日本人なら、人と自然が共生する里山の風景を見たとき、“いいなぁ”と思うでしょう。われわれの原風景がそこにあるからです。でも今は西洋化によって、そういったものがどんどん失われていっている。そこで日本の地方にあるいいものを見つけて、世界に向けて発信したいと思い、シーナリー・ジャパンを立ち上げました。具体的には有田町の文化交流アンバサダー、丹波や京都の織物を使ったインテリア、東京のいいものを紹介する江戸東京きらりプロジェクトやブランディングなどに関わっています。三越で20年、エルメスで20年やったので、これからの20年は日本の社会の役に立つことがしたい。特に若者たちを元気づけたいですね」
日本には数少ない、世界を舞台にプレゼンテーションできる方だけに、ますますのご活躍を期待してしまいます。
そういえば、齋藤さんの私生活も実にインターナショナル。奥様はドイツ人(前妻はフランス人)で、3人いるお子様は4か国語を話すというから、一体どんな生活を送られているのでしょう?
「家では、フランスにいる時は日本語を、日本にいる時はフランス語を話します。お客様が来た時は英語です。私だけドイツ語ができないので・・」
ああもう、想像がつきません!
※当ブログは、B.R.ONLINEでも御覧いただけます!